感情の再評価の概念を知ったきっかけ
youtube中毒な私。
職場での悩みを抱える私にとっては、どうすればいいか考えながら答えを探して、たくさんのyoutubeを見る。
メンタルケアの関係の動画を見ていたときに、内田舞さんという小児精神科医の方の話を聞くことがありました。本も出されているということで、「REAPPRAISALリアプレイザル最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法」(実業之日本社) 読んでみました。
三人のお子さんを育てられているということで、子育て中に起きる感情についての体験も交えながら感情の再評価について説明がされていました。職場での悩みだけでなく、子育てや他のことにも応用が効く手法が紹介されており、これは実践してみたい!と感じました。
毎日バタバタしているので、なかなか感情の再評価ということについて丁寧に考えることもない。頭の中で少し考えてみる程度。実際に文章として書き出してみたほうが、より効果を実感できるのではないかと思い、今日は毎日チャレンジの一つとして感情の再評価を文章にアウトプットしていきます!
「感情」「考え」「行動」に分けてみる
私は再評価をする際には、その状況に対して抱く「感情」、感情の元になっている「考え」、そしてその結果生じる「行動」に分けて分析するようにしています。
引用:REAPPRAISAL最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法 内田舞 実業之日本社
内田先生の本を参考に試しに書き出してみます。
感情・・・子どもがスムーズに登園せずイライラ
考え・・・こちらが話をきいて譲ってまってあげている。上の子も早く行きたいけれど、待ってくれている。上の子が早く登園して外遊びをしたががっているのに、遊ぶ時間がなくなっていしまう。早く感情を切り替えて登園してほしい。元気なのだから休んで家にいるより、幼稚園に行ってほしい。
行動・・・「少し待ってみたけど、もう待てないので早くして。」と怒りながら子どもに話す。泣いているけれど、車に乗せて送っていく。園に着くまでの僅かな時間で、「自分の気持ちだけでなく、お母さんやお兄ちゃんの気持ちも考えて」と理解が難しい下の子に説教をする。
考えの再評価
下の子の登園の際にお兄ちゃんという登場人物がもう一人いたので、再評価をしてみたところ思ったよりたくさんの事柄が出てきました。再評価をしたポイントは以下5点です。
- 「話をきいてあげている」
- 「待ってあげている」
- 「上の子も待ってくれているから早くしなければ」
- 「気持ちを早く切り替えてほしい」
- 「登園するべき」
順番に思いつくことを書き連ねていきます。
「話を聞いてあげている」
話を聞くのは形式的に聞いてみただけで、感情には寄り添っていなかった。私が同じことをされても、子どもと同じような悲しい気持ちになったかもしれない。言葉だけではなく、ハグをしてあげて、涙を吹いてあげればよかったかもしれない。親から感情で離されたら、幼い子供は話の内容より感情をたくさん受け取って、ただ悲しくなるだけかもしれない。
「待ってあげている」
週明けで、下の子供へいつもしている登園前の声掛けを忘れていた。私が上の子の世話に気を取られていて、静かにしていた下の子への声掛けをすっかり忘れてしまっていた。カレンダーもわからない、時計も読めない子どもがいきなり幼稚園に行くと行っても心の準備ができていなかったのかも。だから、下の子が大切にしている登園前ルーティンを時間に余裕を持ってさせるために、早めに声掛けしておくようにスケジュールに入れておく。お兄ちゃんもいろいろとよく覚えてくれているので、私が忘れているときは声掛けを手伝ってもらうか、リマインドしてもらうかで助けてもらうこと。下の子の特性に配慮がかけていたことに気づく。
「上の子も待ってくれているから早くしなければ」
上の子も思い通りにいかないこともあると、知る機会だっかもしれない。こちらが思うほど早くいけないことが悲しいわけではなかったかもしれない。焦って上の子の感情を聞くことしていなかった。感覚ではなく、しっかりと時計を見てあと五分下の子の感情に寄り添ってあげたとしても、上の子はそんなに嫌な気持ちにはなってなかったかもしれない。そして、遊ぶ時間もさほど変わらなかったかもしれない。
「気持ちを早く切り替えてほしい」
感情のコントロールなんて大人でも難しいもの。幼い子供が短時間でそれはできなかったかも。切り替える必要もなかったかも。できる範囲で気持ちの切り替えを促してみて、切り替えられなかったら、切り替えられなかったことも受け入れる。
「登園するべき」
絶対登園しなければならないということはないけれど、子どもの都合ばかりを聞く必要もない。泣く子を見ながら、大人の都合を押し付けるのも少し罪悪感を感じた。休む必要性を親と子のそれぞれの状況に応じて臨機応変に判断すればいい。今日は子どもの気持ちは追いついていなかったけれど、元気だったので登園すればよかったのだと思う。迎えに行ったときの子供の様子をみてまた考えていこう。
再評価で修正した考え
書き出していくにつれ、こう考えるしかなかったと思われるような考え方は他の選択肢もあったのだと気づいていきました。それがわかっていくると、気持ちが冷静になっていきました。
修正した考えは要約すると以下の通りとなりました。子育て中は他の場面でも応用が効くような考えも見えてきました。
- 幼い子供に言葉だけで寄り添う→言葉だけでなく、ボディーランゲージでも寄り添う
- 待ってあげている→カレンダーや時計が読めない子どもがいきなり切り替えできないことを責めない。本人が余裕を持って準備できるよう、こちらも前もってやれることはやっておく。
- 時間に焦る→感覚だけで結構時間がたったと思わないようにする。時計を見るなど事実を確認して、「5分まだ大丈夫」など焦らず余裕を持つ。5分くらいだったら本当は大したことが怒らなかったりするかもしれない。
- 気持ちの切替できないことに不満を持つ→大人でも切替は大変。切替えられないことも受け入れる。
- 登園すべき→時には登園しない日もあっていいという選択肢を持っておく。
うまく行った例を振り返って、「自分がこう考えることで自分の気分のコントロールができた」と気づいたり、あるいはうまくいかなかった例を振り返って、「ここで再評価するんだったな」と反省したりすると良いでしょう。
引用:REAPPRAISAL最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法 内田舞 実業之日本社
自分の「できた」を振り返ったり、時には再評価のタイミングを反省してみたり。まだまだこれからも鍛錬は続いていきそうです。
再評価は認知行動療
まだまだ不慣れではあるが、感情の再評価。なんだか良い感じがした。
「なんだか良い感じがした」というのには、科学的根拠があるようです。
研究によると以下のことがわかっているそうです。
- 最初に、感情を生み出す脳の扁桃体の神経細胞が発火し、活動が活発になる。
- 次に、感情をコントロールする前頭前野の神経細胞が発火し、活動し始める。
- 次第に、扁桃体の神経細胞の発火が収まっていく
引用:REAPPRAISAL最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法 内田舞 実業之日本社
前頭前野と扁桃体の連携を鍛える。
再評価が苦手な人は、扁桃体と前頭前野の活動領域が同時に活性化。
再評価が得意な人は、扁桃体と前頭前野の活動領域が独立して活性化。
前頭前野の活動が活発な人ほど再評価が得意である。
認知行動療法やそこから派生したさまざまな技法を使い、その人の凝り固まってしまった考えを見つめ直し、同じ状況に対して違う考え方もできるということを知ってもらう。また、少ない選択肢の中で行動してきた方に、白黒つけずに柔軟に行動できることもあるという気づきを促していく。
無理に考え方を矯正するのではなく、自分の考えが構築されるきっかけになった今までの経験に向き合うことで、異なる視点もあることに気づくこと。そして、個人個人の認知をよりネガティブなバイアスの少ないものえと変えていくイメージです。
柔軟な視点と考え方が身についてくるとストレスに上手く対処できるようになります。このようなプロセスが最近の認知行動療法の手法で、再評価もその一つの要素なのです。
認知行動療法は、最もエビデンスが集積している心理療法で、認知行動療法をする前と後で脳機能が変わるということが多数の研究論文で示されています。
引用:REAPPRAISAL最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法 内田舞 実業之日本社
メンタルヘルスを保つうえで認知行動療法は効果的であることが証明されている。
再評価を行っていく子で、脳が鍛えられて自分がより良い時間を過ごせるようになっていくなんて、素晴らしい。
再評価で自分の感情や状況を捉え直したら・・・
再評価以前に感じていたモヤモヤは収まりました。
すべてがきれいに解決というわけではありませんが、前向きに問題可決していく方法を前より冷静に考えることができました。
人に話すことで問題解決の糸口を探ることはよくありますが、自分自身との対話によっても、前向きな解決方法を探ることができることを実感。
人に相談することは、相手がいないとできないし、相手の時間も使ったり、時には負担をかけ嫌な気分にさせることもあるかと思います。
人によって脳機能に生物学的な差異はあるとしても、人間は自分の思考を使って前頭前野を活性化させ、よりうまく「考える」脳部位である前頭前野と「感じる」脳部位の扁桃体の連携を鍛えることができますし、こういったことの反復で少しずつ再評価が上手くできるようなっていくということは私自身が実感しています。
引用:REAPPRAISAL最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法 内田舞 実業之日本社
人に相談するだけではない、一人カウンセリングのようなスキルが身につけばより良い人生の時間が増えていきそうです😀
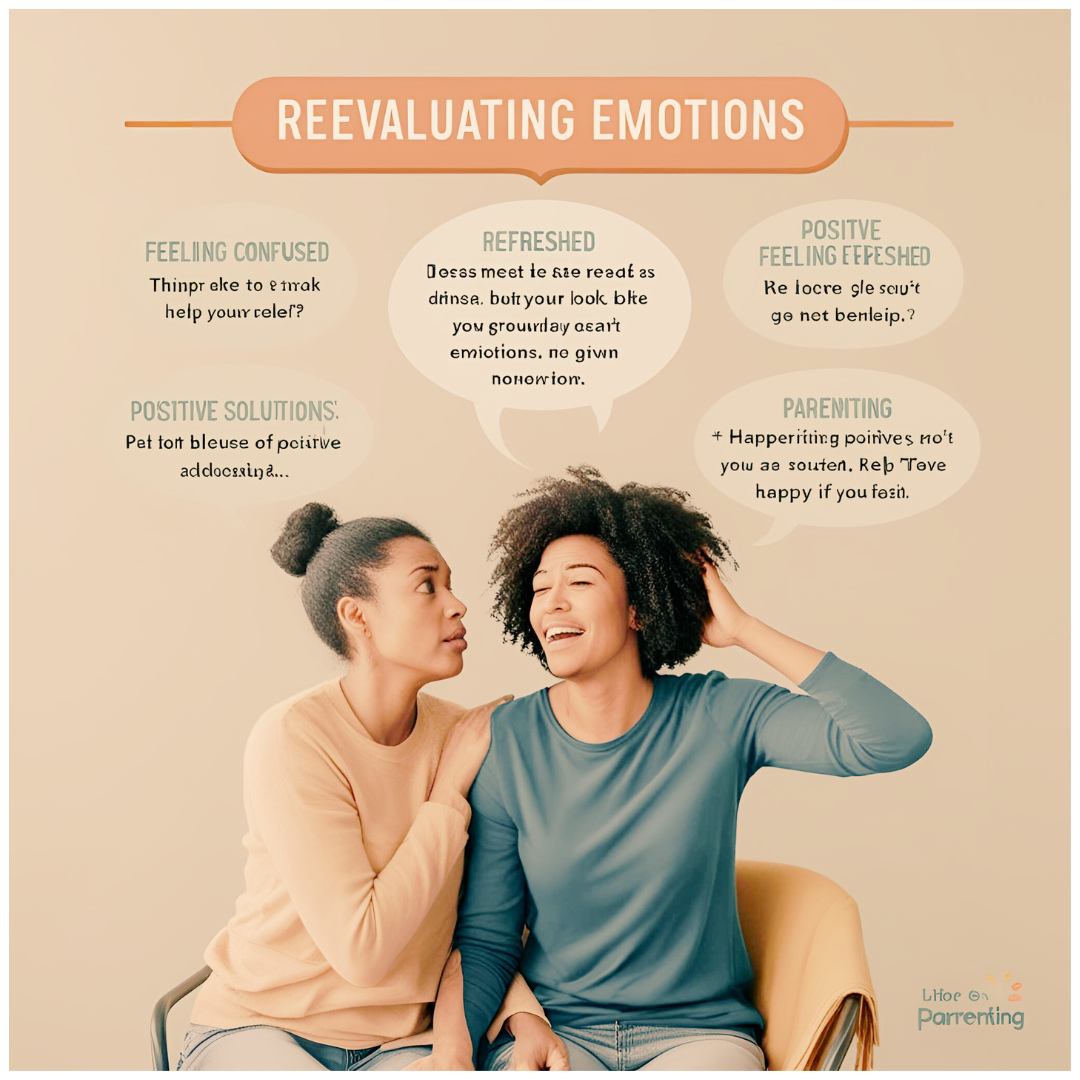
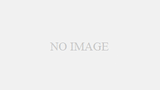

コメント